takuya maeda - sociology
前田拓也(社会学)の研究 / 仕事 / 業績など
books 単著
前田拓也, 2009, 『介助現場の社会学——身体障害者の自立生活と介助者のリアリティ』生活書院.
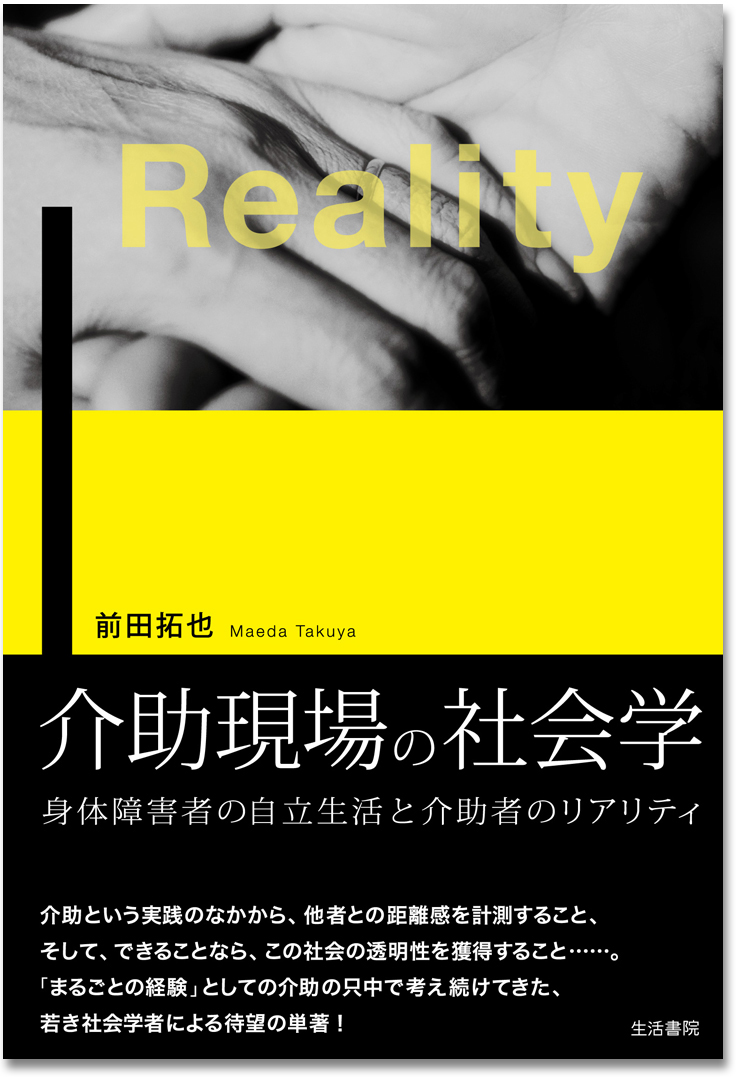
- 【目次】
- 序章 介助、その「まるごとの経験」
- 0 はじめに
- 1 障害者運動と自立生活
- 第1章 介助者のリアリティへ (→ 初出[前田2006])
- 0 健常者というnobody?
- 1 「介助者=手足」論——介助者の「匿名性」
- 2 介入とパターナリズム
- 3 「一人で暮らすこと」と「理念」のあいだ
- 4 介助者のリアリティへ——〈において〉の視座
- 第2章 パンツ一枚の攻防──介助現場における身体距離とセクシュアリティ (→ 初出[前田2005])
- 0 フラッシュバック!
- 1 「不快」な経験
- 2 介助のリアリティ/セックスのリアリティ
- 3 「最前線」としての入浴介助
- 4 パンツ一枚の攻防
- 5 脱構築のパンツ
- 6 「まるごとの社会」のために
- 第3章 ルーティンを教わる
- 0 現場の日常、退屈なルーティン
- 1 ルーティン化の過程——教え、教わる労力
- 2 伝えることの困難
- 3 「現場」のフレームのために
- 第4章 アチラとコチラのグラデーション (→ 初出[前田2006])
- 0 アチラ側へ
- 1 支援費制度と障害者自立支援法
- 2 「技術」のある風景
- 3 わかること・わからないこと・わからなくてもいいこと
- 4 世話の途上、素人の発見
- 第5章 「慣れ」への道
- 0 排泄介助に「慣れる」
- 1 ダーティーワークと生理的嫌悪
- 2 てぶくろを差異に
- 3 ま、いっか、のココロ
- 4 曖昧な慣れかた——慣れるのはよいことか
- 第6章 出入りする/〈介助者〉になる
- 0 人いきれのなかで
- 1 CILというコミュニティ
- 2 障害者コミュニティのなかの介助者
- 3 参加する/そとへつなぐ
- おわりに——「まるごとの経験」のために
- 1 介助の両義性を位置づける
- 2 「介助」の偏在に向けて
- 参考文献
- 序章 > はじめに (pp10-14)
※第1回 福祉社会学会奨励賞 受賞
46判上製
376頁
¥2,940
ISBN 978-4-903690-45-2
C0036
[版元] [CiNii Books]
[Amazon]
本書の目的は、「介助」をめぐって取り交わされる人びとの社会的相互作用に照準したうえで、障害をもつ当事者と、かれらの生——生活と生存——を日常的に支援する者たち、すなわち介助者との関係性がどのように変容し、また、介助の「現場」におけるリアリティは、両者のいかなる実践によってつくりだされているのかを、社会学的に明らかにすることである。
その際、本書が着目するのは、健常者が「介助者になりゆくプロセス」である。「介助者になる」ということは、単に「専門性を獲得する」とか、「障害者のニーズを理解する」とかいったことのみを示すのではない。いわば健常者が、「介助」をめぐって障害者と相互作用を取り交わすことによって生じる自己の立場性やアイデンティティの揺らぎをときに見つめ、ときに疑いながら、それでもなお「現場」にとどまりつづけることによって、障害者との関係性へのフィードバックを繰り返し試みるプロセスのことである。
多くの健常者にとって、障害者はいまだ得体の知れない他者なのだと思う。
たしかに、多かれ少なかれ、あらゆる他者との間には一定の距離がある。距離があるから他者なのでもある。しかし一方で、そのように本来ならば一定に保たれていた他者との距離は、しばしば一気に切り詰められようとされがちだ。そうして、あってしまう、あるいは、あってよいはずの距離を消去することが、つい目指されてしまうのだ。
しかし、仮に「他者と共感し合う関係」なるものがありうるのだとしても、いずれにせよそこへ至る一定の時間、一定の過程を経ることではじめて可能になることであるはずだ。にもかかわらず、その「結果」を語るひとびとは、そこへ至る過程をついつい省略してしまいがちなのだと思う。一定の距離があったはずの「他者」は容易に「共感し合う人間」になって、そのためにあったはずの「時間」は、無かったことになってしまう。わたしの知りたいのは、その「過程」なのにもかかわらず。
そうならない、なってしまわない語り口は、ないものなのだろうか。わたしは、そんなことを考えながら、「介助現場」に、できるだけへばりついてきた。
そうして、わたしには少しだけわかってきたことがある。それは、他者のことをわかる/慣れるために、「現場」でできるだけ長い時間を費やすことの重要さだ。
ただし、急いで付け加えておかねばならないことは、そこで長い時間を過ごせば過ごすだけ、なにかが「免罪」されるわけでもないし、障害者の立場を「代行」する権利を得ることができるわけでもないということだ。場合によっては、いつまでもかまわないでくれ、さっさといなくなってくれ、と思われている可能性すら否定できるわけではないだろう。
そしてもちろん、一定の時間を過ごすことを欲していたにもかかわらず、さまざまな理由で「現場」から離れざるを得なくなった人びとを指弾する権利があるわけでもない。
さらには、そこである程度の長い時間を過ごすことができたのは、わたしの介助者としての働きに「お金」が支払われていたからでもあり、その「お金」は、これまで障害者運動にかかわってきた人びとの絶え間ない努力のたまものでもある。
しかしともかく、介助をおこなうこと、そして、「介助の時間」を——できることならできるだけ長く——過ごすこと。そのただなかで健常者が「介助者になる」というプロセスはそのまま、障害者との距離をはかる営みだと言っていい。そして、介助は、身体を通じて障害者という他者とのかかわりかたを「まるごと」体得する営みでもある。
この「まるごと」には、なにもポジティブな要素だけが含まれるのではない。健常者であるわたしが、障害者の生活において支援し、配慮し、尊重することに意識的に努めたとしても、それでもやはりどうしても差別的であったり、加害的であったり、暴力的であったり、してしまう。「まるごとの経験」には、そんな実践も含まれよう。
たしかに、「現場」に足を運ぶことは、なにより大切なことだ。でも、「現場」が妙に美化されてしまったり、神秘化されてしまったりすることはよいことではない。わたしはもしかすると、その人の目の前にいてなにかしらのふるまいをみせるというただそれだけで、その人にとって有害だったり抑圧的だったりしてしまうのではないか。ましてや、その人を支援しようなど。
しかしそれは、単に「しかたのないこと」だという以上に、この社会における自分の位置取りを知るうえで必要なことなのだ。介助という実践のなかから、他者との距離感を計測すること、そして、できることなら、この社会の透明性を獲得すること。
介助をおこなうなかで、驚くこと、おかしくて笑ってしまうこと、失敗すること、叱られてしまうこと、違和感をおぼえてしまうこと、不甲斐なさを思い知ること、イライラすること。これらはすべて、介助者と障害者の「あいだ」でおこることであり、介助者自身が自身のことばと身体を介して経験したリアリティは、障害者との関係性そのもののなかからはじめて立ち現れてくるのだ。
たとえば、対面的な相互作用の生起する場面を考えてみると、しばしばわたしを含めた健常者はかれらの前でどのように振る舞うべきかわからず、当惑してしまう。かれらと社交的につきあうための「儀礼」を身に付けることができていないのだ。その当惑は、きっと両者の関係性と距離感が引き起こしたものだ。決して出会うことのなかった両者。どちらかが悪い、悪くない、といった問題ではない。わたしたちが置かれたこの社会での立ち位置のありかたが、「当惑するわたし」のなかに凝縮して経験され、表現されているのだ。
いわばこれらは、わたしたちの健常者性(傍点)——健常者中心の「できなくさせる」社会(disabling society)と、そうした社会が規定する人びとの価値・規範および行動様式の総体——とでも呼びうるものだ。
だから、その当惑を自覚したり、押さえ込もうとしたり、相手と反発しあったりして、その「わたし」のありようを変えてゆこうとするプロセスは、わたしの目の前にいるまさにその人との関係性を変えてゆくプロセスのことであり、それはそのまま、この社会の中で位置づけられ、再生産される両者の関係性を組み替える試みへと、静かにつながってゆく。そう言っていいと思う。
そんな問題意識から、本書をはじめてみよう。
.....
review
referred